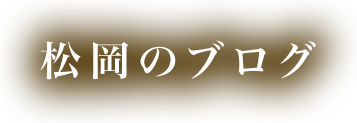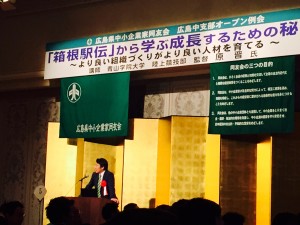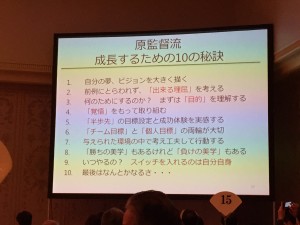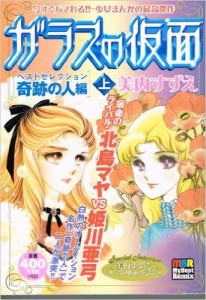皆様,こんにちは。
レジリエンス研修講師,ポジティブ心理学コーチの松岡孝敬です。
昨日,2月22日,広島県中小企業家同友会の例会があり,
会員として出席させていただきました。
その会では,青山学院大学陸上部監督の原晋氏をお招きし,講演会が開かれました。
原監督の指導法は,ポジティブ心理学コーチングやポジティブ組織論の
コンサルティングに通じる試みがあり,とても興味深く拝聴しました。
ご存知の方も多いですが,原氏は,今年の箱根駅伝で青山学院を一度もトップを
譲ることなく完全優勝で2連覇に導いた,今や時の人となった陸上界の異端児です。
お話を聞いていると,とてもレジリエンスの強い方だなあと感じました。
中京大学陸上部を経て地元,中国電力陸上部の1期生として入社するも,
27歳で故障し,事実上のクビを宣告され,一から関連会社の営業として
左遷同然で流され,そこで抜群の営業成績を残して、社内ベンチャー企業のメンバーに
抜擢されてそこでも結果を残すことになります。強烈なレジリエンス,負けじ魂ですね。
それで終わることなく,高校時代の後輩からの話で,低迷していた青山学院大学陸上部の
再建のため,監督就任のオファーが入ります。
一度は忘れかけていた陸上への情熱がふつふつと沸き起こり,
当初は大学の嘱託職員扱いという極めて低い条件の身分で,
家族の反対を強引に説得し,退路を断って青山学院陸上部の監督に就任します。
当然のごとく,順風満帆なチームづくりとはいかず,当初はさまざまな困難・
試練に会いますが,10年計画で戦略的にチームをつくっていき,
2015年大学駅伝2冠,箱根駅伝2連覇と輝かしい業績を立てられました。
最近,講演があると,話を聞きながら演者の“強みスポッティング”をするのが
癖になっているのですが,原氏のお話からは,「忍耐力」,「計画性」,「勇気」,
「情熱」,「大局観」といった強み(キャラクターストレングス)が感じられました。
指導法もユニークで,「ハッピー大作戦」と称して,選手の幸福度(ハッピー指数)を
自己申告させて,選手のモチベーション,ポジティビティを上げたり,
「コカ・コーラ大作戦」と称して,選手の力を120%引き上げるような試みをしたりと,
まさにポジティブ心理学ベースの介入法,ポジティブ心理学コーチングと感じました。
自らを「ファーストペンギン」に例える陸上界の異端児は,まさにポジティブ組織論
でいう,“ポジティブな逸脱”(Positive Deviance)をしている方。
そして,そんなポジティブな逸脱者は,選手の自主性を重んじ,
ポジティブな組織文化を醸成し,コカ・コーラから炭酸が一気に噴き出すごとく,
選手のパフォーマンスを一気に最高潮に高めます。
残念なのは,日本の教育界,企業文化が,こんなポジティブな逸脱者,
異端児を育成するような社会になっていないことです。
私は,微力ながら自分のコンサルティングやレジリエンストレーニングで,
そのような文化を変えていきたいと思っています。ていうか変えます。