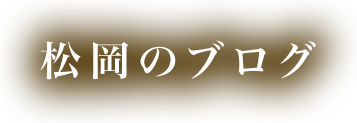2015.5.25
久しぶりのブログ。
先週は東京遠征で忙しく,心身ともに疲れ切ってしまったのでブログを書く気持ちが起こりませんでした。こんなことではいけないと思い,気持ちを引き締めてブログ更新の頻度を高めていこうと思います。
最近,商談などで,「ポジティブ心理学をベースにしたレジリエンス・トレーニングはポジティブシンキングと何が違うのですか?」という質問をよく受けます。また,「ポジティブシンキングの伝道師たる松岡さんが,○○さんのネガティブキャンペーンをはっている○○を支持するのはどういう訳なんですか?」といった質問も受けたことがあります。その都度,ポジティブ心理学とポジティブシンキングの違いを説明していますが,やはりまだまだ誤解される方が多いようですね。
ポジティブ心理学者は「ポジティブシンキング」という言葉が嫌い?
マーティン・セリグマンやバーバラ・フレデリクソン,イローナ・ボニウェルなど著名なポジティブ心理学者の著書を読むと,必ずといってよいほどポジティブ心理学とポジティブシンキングとの違いに言及している印象があります。これは,多くの一般の人々が持つ,「ポジティブ心理学って,ポジティブシンキングのことでしょ?」という偏見に対して,ポジティブ心理学者が悩まされている証左でしょう。正直,このような偏見・誤解には,ポジティブ心理学者は迷惑に思っているだろうし,「ポジティブシンキング」という言葉と,その言葉が発する“ネガティブなイメージ”とポジティブ心理学とを同視する誤解に対して,辟易としていると思います。
私もポジティブ心理学者と同感で,「株式会社ポジティビティが提供するサービスと,ポジティブシンキングとは同じでしょ?松岡さんはポジティブシンキングの伝道師なんでしょ?」と思われると本当に残念な気持ちになります。私の(そして弊社の)ミッションは,『レジリエンスの高い人々,ポジティビティ溢れる繁栄型組織を育て,双方の持続的成長にコミットする』ことですが,私はポジティブシンキングの伝道師ではないですから。
では,ポジティブ心理学とポジティブシンキングって何が違うのでしょうか?
私は,ざっくり,「科学的証拠(エビデンス)の有無」と,「ネガティビティの扱い方」の2つと考えています。
科学的証拠の有無
ポジティブ心理学は,1998年に提唱された心理学の新たな潮流ですので,れっきとしたサイエンスとしての心理学の一分野です。つまり科学なのです。ポジティブ心理学をベースにしたさまざまなワーク,心理テスト,アセスメント,トレーニングプログラムは,膨大な人と時間を費やして調査された実証データに基づいて開発されています。私どもが提供するレジリエンス・トレーニングプログラムも,ポジティブ心理学,レジリエンス研究,PTG研究,行動認知療法のエビデンスをベースにして開発されています。
一方,ポジティブシンキングとは,各々個人が,自分自身の経験や判断をもとに自分の(ポジティブな)価値観や信念を主張・提唱するものです。したがって,個々人の考え方ですので,ベースに根拠がある場合と単なる思い付きの場合があります。根拠がある場合も,個人の経験則の場合がほとんどで,科学的に実証された結果には及びません。
まとめますと,ポジティブ心理学は科学という学問で,ポジティブシンキングは根拠に乏しい個人の考え方と言い換えることができると思います。
ブログが長くなったので,もう1つの違い「ネガティビティの捉え方」の説明は,次回のブログに続けます。
2015.5.18
先日,ビジネスコーチの学友のグループの好意で,関西の勉強会に招かれ,レジリエンスの講義をさせていただきました。ビジネスコーチの資格を持っている方やプロフェッショナルで活躍されている方が多く,それぞれが,人や組織を生き生きと活性化させたいという共通の志を持っているので,大変熱心に聴いていただき,気持ちよく講義をすることができました。
レジリエンスは超一流の成功者の必須要因
講義の中で,レジリエンスの強い著名人やスポーツアスリートの例を挙げ,「レジリエンスは超一流の成功者の必須要因」ですと紹介すると,数名の方に響いたのか,いろいろなところで取り上げていただいています。嬉しいですね。
自分でも,講義のためのパワーポイントの資料をつくっていて,大記録を達成したり,人々を感動させた超一流のスポーツアスリートや,世界を驚嘆させたイノベーションや大発明を起こした科学者や経営者は,例外なくレジリエンスがとても強いことを再認識しました。成功したからレジリエンスが強くなったのではなく,レジリエンスが人一倍強いからこそ成功したのだと判断しています。
ポジティブ心理学では,よく「成功したから幸福なのではなく,幸福だからこそ成功する」と言われます。幸福度が高いほどレジリエンスも強化されますので,前の言葉は,「成功したからレジリエンスが強いのではなく,レジリエンスが強いからこそ成功する」と言い換えることができると思います。これは真理だと思います。
ストレングスカードの効果
講義では,レジリエンス・トレーニングの一部を体験してもらうため,ストレングスカードを用いた自己の強みの確認と活用を検討するワークをしていただきました。50枚のストレングスカードを並べると,強みというものが50種類もあるのかと視覚的に理解でき,驚いたとの声をいただき,とても好評でした。

自分のライフワークとして選んだ仕事が充実した素晴らしいものと実感できた一日でした。関西のビジネスコーチの学友の皆様,本当にありがとうございました。感謝感謝でございます。
2015.5.14
最近,パソコンの調子が悪く,仕事もはかどらず,ブログも書けず,フラストレーションがたまる日々が続いています。感情のコントロールが難しい,レジリエンスが試される期間ですね。
入社前研修で重要なこと
最近の多くの企業では,内定者の人材マネジメントとして,配属面談,入社前メンター制度などのプログラムを実施しているところが多く,内定期間中に実施される入社前研修も広く普及されているようですね。私が入社前の内定者の頃は,バブルのまっ盛りなので,内定者研修と言えば,派手にお金を使い,アゴアシ付きで飲み食いさせてとにかく内定を取り消さないようにすることだけが目的の,研修とは名ばかりの宴会・懇親会でしたが,最近は違いますね。
最近の入社前研修は,楽しい宴会の雰囲気は薄くなり,しっかり教育・研修をしています。その中身は,資格取得支援,e-ラーニング,通信教育,課題レポートの提出,合宿研修,現場・店舗見学,現場実習などです。入社前から入社後即戦力になるようけっこう鍛えてようとしていますね。研修を行う側の企業の目的としては,内定期間の不安解消やモチベーションの中だるみ防止,他社に関心がいかないようにするための囲い込み,入社後の能力・スキルのばらつき防止などだそうです。
おそらく最後の囲い込みや能力・スキルのばらつき防止が主な目的ではないかと思います。早々と離職されるよりは先手を打って入社直後からしっかり働かせて費やしたコストの元をとってやろうぐらいしか思っていないんでしょうね。だったらコストのかかる入社前研修などやめてしまえば良いのに。日本の企業は未だに人は現場にでないと育たないとして計画的戦略的な人材育成が苦手なんだなあと研修の情報を調べてて痛感しました。
内定時には経営理念やビジョン・ミッションを共有させれば
入社前に現場実習を経験させて成功体験をつめば自信につながるとは思いますが,強烈な失敗をしてそれをケアするような研修をしなければ,かえって逆効果で入社前から自信を失い,無力感・敗北感などのネガティブ感情が蓄積し,離職につながります。
なぜ,企業は,入社前に役に立つかどうだかわからないけど学生が望むような資格取得支援をしたり,即戦力やスキルアップにはつながるかもしれないが自信を喪失させるかもしれない現場実習に拘るのでしょうか?そんなことをするよりも,企業の経営理念とかビジョンとかミッションとかクレドを共有するような取り組みをした方が良いように思います。それも打ち解けたポジティブな雰囲気で。内定しているとはいえまだ社員ではないので,がっつり「我が社のビジョンとは何か」なんてテーマでディスカッションすると内定者も引いてしまうけど,のんびりワークや遊びを入れてビジョンとかミッションの共有をすれば,内定者どうしの結束も高まって個々人のレジリエンスも強化され,会社への貢献意欲も高まり,組織レジリエンスも強化され,結果,離職率も減少するのに。
実は,持続的に繁栄している企業,エクセレントカンパニーは,このような入社前に企業のビジョン・ミッションを共有するようなプログラムを実行しています。だからこそ,社員が生き生きと働き,従業員幸福度も顧客満足度も高く,成長していけるのでしょう。
経営理念・ビジョン・ミッションの共有を行っていない企業は,察するに,「①ビジョンの共有なんて重要でない」と思っているか,「②ビジョンなんて対外的なものなのだから社員に共有させる必要はない」と思っているか,「③そもそもビジョンを明確化していない」のいずれかでしょう。
③のビジョンが明確化されていない企業は,悲しいですね。そのような企業は,企業のトップのキャラクターや価値観・世界観がビジョンになり経営理念になります。トップの人格が素晴らしければ良いんですが,ビジョンを明確化していない企業のトップの世界観・価値観は,どことなく社会に対する後ろめたい背徳感が感じられる場合が多いです(だからビジョンを明かさないのかも)。少なからずさまざまなタイプの企業と,その企業のトップと接してきた私の実感です。
2015.5.12
ドラッカーに訊け!
かつて経営学者,ピーター・ドラッカーは,こう言いました。
「何事を成し遂げられるのは強みによってである。弱みによって何かを行うことはできない。」
ポジティブ心理学においても,強みを理解し,活用した方が,弱みをなくすことよりも,よりポジティブな結果や人生での成功に貢献できることがわかっています。
「強みって,私には,特段強みってないよ。」と消極的なことを思う人もいるかもしれませんが,どんな人でも強みはあります。
人格としての強み(キャラクターストレングス)
ポジティブ心理学においての強みとは,キャラクターストレングスといって,人格としての強み,強みとしての徳性・美徳といわれています。
強みの診断には,いろいろなものがありますが,無料でできる診断にVIA-ISというものがあります。これはネットで無料で行えます。VIA-ISの強みの中には,「創造性」,「リーダーシップ」,「忍耐力」,「社会的知能」など,強みやいわゆる長所として納得できるものもありますが,「感謝」,「愛情」,「希望」など,強みを長所ととらえているとおやっと思えるものもあります。ですが,「感謝」,「愛情」,「希望」というポジティブ感情が多いことも強み(人格としての強み)になるのです。
このような強みでしたら,入社まもない新入社員も診断できます。入社前に診断して仕事の配属に生かすこともできますよね。
真の強みとは,ポジティブな性格の特徴で,真正さとエネルギーを感じさせると言われています。自分の強み(人格としての強み)を理解し,それを活用することは,レジリエンスを強化することにもつながります。それだけでなく,幸福度を高めることにもなります。
したがって,新入社員の強み(キャラクターストレングス)を新入社員自身も会社組織も把握し,それを職場で有効に活用できるようなしくみづくりなり配慮をすれば,新入社員は生き生きと仕事にチャレンジすることになり,離職にはつながらないと思います。
2015.5.10
かつて,元マレーシア首相のマハティール氏は,マレーシアを訪問した日本の首相が相も変わらず先の大戦の謝罪をすることに対して,「日本はもう謝罪する必要はない」と言い放ったそうです。同時期に,台湾の元総統,李登輝氏も同じようなことを日本に発していました。李登輝は戦前,京都大学に留学し,日本の植民地時代だった台湾のことはネガティブにはとらえていません。マハティールも東南アジアに進出した日本を帝国主義的な侵略者とはとらえておらず,それどころか,当時の日本を評して,
「日本の成功は東南アジアに大きな自信を与えた。日本の進出がなければ欧米の世界支配はさらにつづいていただろう」
「日本の戦争責任を問うならば,それ以前,非人間的な支配と収奪をつづけた欧米の宗主国の責任はどうなるのか。日本が来たことで植民地支配から解放され近代化がもたらされた」素晴らしい政治家ですね。
マハティールのような政治家こそが正しい歴史認識をもっている稀有な人物と思います。マハティールも李登輝もポジティビティ溢れる政治家で,短期間のうちに,それぞれの祖国を経済的に著しく成長させ,繁栄へと導きました。しかも,ほとんど大国の経済援助に頼ることもなく。
話題は変わり,日本海を挟んだ隣国のことが今夜のニュースで報じられていました。未だ日本統治下の時代を悪と評し,偽りの歴史事実をプロパガンダし,日本と共通の同盟国であるアメリカにもロビー活動している国のことです。偽りの歴史事実を掲げて反日感情を煽り,経済面での失政からくる政権批判の矛先を日本に向けさせている国のことです。極めてネガティビティ比の高い国ですね。歪んだ日本に対するネガティブ感情を高めることしか国をまとめあげることができないなんて。
今夜のニュースでは,かの国では,2つの疲れが蔓延しているとか。1つは「反日疲れ」。国民は,もう政府の反日には疲れてうんざりしているとのこと。そんなことよりそろそろ本腰入れて経済を立て直せよと思い始めているそうです。国民は政府が考えているほど愚かではないということでしょう。もう1つの疲れとは,「アメリカの○国疲れ」を国中が敏感に感じているそうです。先日のアメリカ議会での安倍総理の演説が高く評価されていることに,隣国のメディアはナーバスに報じているようです。アメリカは日本の隣国にそろそろ愛想をつきつつあるとか,かの国の反日プロパガンダに疲れているとか。隣国のメディアは,かの国の外交は短期的な戦術も長期的な戦略も敗北しているとの論調だそうです。深く納得できます。ようやく気づいたかと。かなり遅きに失したと思いますが。
安倍総理の米議会での演説は,過去の反省を交えつつ,将来のビジョンを示したもので高く評価されるのも理解できます。ネガティビティもあるがそれを上回るポジティビティ溢れる演説でした。政治的な業績はまだまだ評価できませんが,あの演説は評価されてもよいと思います。
ポジティビティが溢れる人や組織は,レジリエンスが強化され,持続的に繁栄していきます。これは真理だと思います。かの国の政治家が,マハティールや李登輝のような正しい歴史認識をもつようになり,ポジティビティが高まり,我が日本と良好な関係になることを切に望みます。
今夜のニュースで,隣国のとある観光地で日本統治下の街並みを再現したところ,観光客が増えて経済的に潤ったとか。その地の観光ガイドは,日本統治下の当時のことを土地の人は誰も悪く言う人はおらず,むしろ良い印象があったので,思い切って日本家屋などの日本統治下の街並みを再現したとか言ってました。かの国では,政治家よりも一般人の方が正しい歴史認識をもっているのかもしれません。